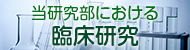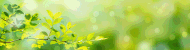精神科医
当研究室で活躍する精神科医の声を紹介します。普段は所属元の医局で勤務しながら、週に1回など定期的に当研究室に来て研究指導を受けている社会人国内留学の精神科医や、数か月~1年といった特定の期間、所属医局から出向して研究員としての雇用で当研究部に在籍し、留学後にまた所属医局に戻って活躍されている精神科医もいます。既に学位取得後で研究歴がある程度あっても、さらなる発展的な学びを求めて週に1回などのオンラインフェローで遠隔指導を受けている精神科医もいます。のんびり楽しみコースもありますので、ちょっと研究に興味ある、一度環境を変えてみたい、などといった希望も大歓迎です。1人1人の精神科医の先生たちの最適な学び方について、所属元の教授・指導教官も交えて相談に応じています。
研究生等の立場での週1回など定期来所の国内留学
週に1回など定期的に当研究室に来ていただき、研究指導を受けて研究活動に取り組んでいる精神科医が活躍しています。どのようなキャリア段階でもその方のバックグラウンドに合わせて個別に対応しています。首都圏の先生で、週に1回程度通える場合は特に推奨していますが、中には新潟県から定期的に通っている精神科医もいらっしゃいます。
精神科医2年目から始めた先生の声
地方にある病院精神科のと申します。精神科医として4年目になります。
私は精神科専攻医2年目の際、半年間、NCNP病院に出向する機会をいただきました。その折、以前から臨床研究に興味があったため、橋本先生、松本先生にご相談したところ、快く研究指導をお引き受けくださり、精神疾患病態研究部の研究生として、週に1度、臨床研究のご指導を頂けることになりました。
臨床研究に関して全くの初心者であった私に、橋本先生、松本先生をはじめ、研究室スタッフの皆さまが基礎から大変丁寧に教えてくださいました。
半年間のNCNPでの出向を終え、自施設へ戻ってからも、引き続き月2回、研究生として研究活動を継続しております。
現在は、橋本先生が研究代表を務めておられる精神疾患データベース研究に、自施設も参加させていただいており、自施設での臨床研究体制を整え、症例の収集を進めています。先日は、収集したデータを解析し、国内学会で発表する機会も得ることができました。
精神科医になったばかりの私のような、地方病院に在籍する者でも、このように研究に参加させていただける大変恵まれた環境です。研究に興味をお持ちの先生方がいらっしゃいましたら、ぜひともご一緒に研究に取り組んでまいりましょう。
2025年11月21日
研究生(週1回:国内留学)
精神科医3年目から始めた先生の声
大学精神医学講座、同大学院3年生のと申します。現在医師8年目、精神科6年目です。自大学ではリサーチレジデントとして研究と病棟・外来を兼務し、大学院1年目の秋からは毎週水曜午後の週半日で、精神疾患病態研究部に通っています。当部に関心をお持ちの先生方の参考になればと思い、当部の研究生となった経緯とこの2年間を簡単に振り返らせていただきます。
研究志向でなかった私が今に至る大きな一つの転機が、精神科1年目に受講したEGUIDEでした。同時期に自大学の薬理班で処方調査の手伝いをしていたこともあり、エビデンスプラクティスギャップを埋め、適切な治療を広く届けるというEGUIDEの理念に心を打たれました。研究・教育が臨床に直結するやりがいと面白さを感じ、後期研修が終わると同時に自大学の大学院に進学しました。まずは自大学の処方調査を1本、論文としてまとめましたが、やはりEGUIDEの本丸である当部で学びたいと考え、自大学での臨床と研究の合間を縫って当部に通わせていただくこととなりました。
万単位のビッグデータを扱うEGUIDEのスケールに心躍る一方で、部長から「すぐ解析に入るか、基礎トレーニングから始めるか」と問われ、自らの立ち位置を知るために後者を選択しました。ここで驚いたのが、事務・心理士を含む多職種で、データ取り扱いに関する共通の基礎トレーニングが整備されていたことです。まず約2か月、Excelでの緻密なデータ管理を徹底練習し、続く約2か月でEGUIDEデータのダブルチェックを担当し、既に多数刊行されているEGUIDEの既報を集中的に読み込みました。この頃から、EGUIDEの中でもガイドライン一致率に興味を持ち、週半日と別に月1回の定例ミーティングにも参加するようになりました。当部に通い始めて半年が経った頃から、自分のテーマを持って研究を開始しました。
EGUIDEデータ解析に進む前段として、まずは生データに手で触れることを重視し、自施設の患者250例のガイドライン一致率を半年かけて調査し、学会発表しました。次いで、ガイドライン一致率とDIEPSSの関連の解析に取り組み、こちらも学会で発表予定です。いずれも論文化を進め、投稿中です。現在はEGUIDEの各ミーティングに顔を出させていただき、解析にも携わっています。
正直、最初の半年は「早く解析したい、論文を書きたい」という焦りもありました。しかし、基礎を徹底した下積みがあったからこそ、今、複数の原稿を並行して進めつつ次の研究に踏み出せているのだと思います。週半日とは思えないほどの丁寧かつ熱量高いご指導のおかげで、2年前の自分と比べて明らかに実力が付いたと実感しています。以上、週半日×2年間での進捗と所感のご報告でした。先生方のご検討の一助となれば幸いです。
2025年9月10日
リサーチレジデント・大学院生 、研究生(週1回:国内留学)
精神科医6年目から始めた先生の声
普段は精神科医として勤務し、精神疾患病態研究部には1年ほど研究生としていくつかのプロジェクトに従事させていただいています。これまで蓄積されてきた大規模なデータを解析させていただく機会があり、その情報量に驚くとともに、臨床疑問をデータで検証することができる面白さを感じます。また多忙な中でも指導にリソースを割いていただき、研究データの扱い方など研究者としての基本的姿勢についても身につけることができました。研究部内だけでなく、COCOROやEGUIDEといった大学を超えた研究・臨床ネットワークの中で様々な先生方と交流の場があることも大きな魅力の一つだと思います。定期的に開催される精神病態セミナーでは、精神医学研究の第一線でご活躍される先生方のお話を聴講することができます。精神医学研究者として駆け出しの私にとって、精神疾患病態研究部での経験は本当にかけがえのないものになっています。
2023年1月7日
講師、研究生(週1回:国内留学)
研究員の立場で数か月~1年などの期間を決めた短期国内留学
数か月~1年といった特定の期間、所属医局から出向して研究員としての雇用で当研究部に在籍し、留学期間満了後にまた所属医局に戻って活躍されている精神科医もいます。所属元の医局の教授・指導教官とも意向をすり合わせて、その先生の希望に合わせた多様なキャリア形成に対応しています。
精神科医1年目から始めた先生の声
大学精神神経医学講座レジデントのと申します。私は初期臨床研修を修了後、大学精神神経医学講座に入局し、同時に大学院に進学しました。また、入局初年度の1年間は、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神疾患病態研究部に国内留学する機会をいただきました。
通常、入局直後は精神科専門医研修や精神保健指定医取得を目指して臨床に専念し、大学院生であっても研究は並行して少しずつ進める形が多いかと思います。私も当初はそのような予定でしたが、当科教授のお勧めにより、国内留学という貴重な機会を頂きました。精神科の経験がほぼ無い自分では役不足ではないのか…という不安がありましたが、「やらないで後悔するより挑戦してみたい」という思いでその道を選びました。
留学先ではまず、Excelを用いた緻密なデータ管理を徹底的に練習し、報告・連絡・相談の重要性や、確認作業・ダブルチェックの大切さ、落ち着いて物事を考える姿勢など、あらゆる仕事に通じる基礎を学びました。その後は研究員として精神疾患の脳画像研究に携わり、退職までには約5,000例の精神疾患群および健常対照群の脳MRI画像を診るという経験をしました。臨床では到底得られない膨大な画像を拝見できたこと、また「精神疾患データベース」に少しではありますが携わらせていただけたことは、当初自信のなかった私にとって大きな成長のきっかけとなりました。
現在は医局に戻り、精神科臨床を中心に勤務しつつ、週1回、研究生として遠隔で研究用プロトコールによる脳MRI画像を学ばせていただいております。NCNPでのご指導を通じ、医師としての基盤を築くことができたと感じております。
もし今後、国内留学に挑戦するか迷っている方がいらっしゃいましたら、私のように未経験でも温かく迎え入れ、熱心にご指導くださる環境ですので、ぜひ一歩踏み出していただければと思います。
2025年10月5日
レジデント・大学院生、研究生(1年間:科研費研究員の立場で国内留学→週1回:オンラインフェロー)
客員研究員等の立場での週1回など定期的な遠隔指導
既に学位取得後で研究歴がある程度あっても、さらなる発展的な学びを求めて週に1回などのオンラインフェローで遠隔指導を受けている精神科医もいます。普段は大学や病院で指導的立場で活躍しながら、リモートで研究指導を受けるオンライン国内留学形式です。
精神科医9年目から始めた先生の声
病院精神科と大学地域精神医療学講座に所属すると申します。医師12年目、精神科10年目です。これまで臨床を中心に歩んできましたが、研究の面白さに惹かれ、30代半ばを迎えた今、今後のキャリアをより深く考えるために研究力を一段階高めたいと考え、NCNPのオンラインフェローに参加しました。
現在は橋本先生から週1回のオンライン面談による遠隔指導を受け、自施設での臨床と研究を両立しています。指導を開始してから1年が経ち、研究の考え方や進め方が大きく変わり、科研費にも採択されました。
私が取り組んでいる研究テーマは、①EGUIDEの薬剤費削減効果、②EGUIDEのガイドライン遵守治療の改善効果、③ガイドライン遵守治療と行動制限の関連です。毎週の面談では、目的や仮説の検討、研究デザインや解析計画の具体化を進めながら、臨床や社会的視点を研究に取り入れる方法、再現性のある研究計画書の作成、効率的な文献検索と批判的読解、国際誌にまとめるための書き方、統計解析の解釈などを実践的に学びました。
もともと自分で調べながら一人で研究を進めることは得意でしたが、人から指導を受けたり、共同で研究を進めたりすることには苦手意識がありました。しかし、議事録を作成し次週の目標を共有するスタイルを重ねる中で、共同研究を推進する力が着実に育っていきました。時には厳しいご指導を受け、成果を共に喜ぶ経験を通じて、研究は一人で深めるだけでなく、仲間と築き上げるものだと実感しています。
橋本先生の遠隔指導は、研究立案から計画書作成、文献レビュー、統計解析、共同研究の推進まで、研究者として必要な力を総合的に伸ばしてくれるオーダーメイド型の伴走指導です。この一年を振り返ると、研究の基礎力だけでなく、仲間と共に研究を育てていく力や、研究者としての立ち振る舞いも大きく成長したと感じています。
これからどんなキャリアを選ぶかはまだ決めきれていませんが、この学びを通じて確実に選択肢が広がったと実感しています。研究を自分らしく深めながら新しい挑戦をしたい方には、ぜひこのオンラインフェローでの学びをおすすめしたいと思います。
2025年9月29日
診療部長、客員研究員(週1回:研究者育成道場オンラインフェロー)
精神科医10年目から始めた先生の声
大学精神神経医学講座のと申します。EGUIDEを通じて2023年4月から精神疾患病態研究部と関りを持たせていただいています。当初はガイドライン普及活動のみを行っていましたが、途中から研究活動にお声がけいただき、統合失調症のガイドライン一致率に関する研究を開始しました。その際は橋本先生および大学
N先生に御指導を頂きました。エクセル機能を駆使した見やすい図の作製法を教えて頂きました。研究結果は2025年3月にJournal of Psychiatric Researchに受理されました(https://byoutai.ncnp.go.jp/eguide/Kawamata2025_abstract.html)。
査読期間が長く論文採択までには時間を要しましたが、エクセルで見やすい図に作り直して過去の研究結果をポスター発表したところ2023年11月第36回日本総合病院精神医学会総会にてポスター賞を受賞することができました。教えていただいた技術で直ぐに結果を出せたことは幸運だったと思います。
このように他の研究でも応用できる技術を学べることは地味ではありますが大きな魅力だと思います。その他にもデータセットの効率的な作り方を教えていただきました。教わったデータセットの作り方も含めて日本精神神経学会の初学者向けシンポジウムで発表したところ、後日会った受講者から「データセットの先生」と声をかけられました。受講者も目から鱗だったのだと思います。
2024年10月からEGUIDE研究者育成委員会が発足し、クロザピンに関する研究を開始しました。科研費の申請もサポートしていただき、実際に採択された申請書も見せていただきました。その際には松本純弥室長にもご相談させて頂きました。精神疾患病態研究部メンバーのみならず、EGUIDEメンバーと交流ができ人脈が広がることも魅力です。現在は大学病院が県のクロザピン普及の拠点病院となるため検査体制の整備を行っており、拝借した検査セットを流用させていただく予定です。その際も惜しみなく検査セットを提供していただきました。
2025年9月29日
講師、客員研究員(週1回:研究者育成道場オンラインフェロー)
精神科医13年目から始めた先生の声
大学医学部精神科学講座のと申します。現在、医師として16年目、精神科医として14年目になります。私は、臨床・教育・研究を三本柱として日々の業務にあたっており、医局長としての運営、病棟長・リエゾン長としての臨床業務、さらに外来診療といった多忙な日常業務を担いながら、EGUIDEプロジェクトなど多施設共同研究にも携わっています。
精神疾患の診療と研究の接点を強く意識するようになったきっかけは、精神科初期の段階で受講したEGUIDE講習でした。当時、診療ガイドラインの普及と実臨床との間に大きな隔たりがあることを痛感し、「エビデンスと臨床のギャップを埋め、より適切な治療を広く届ける」というEGUIDEの理念に深く共感しました。研究や教育が臨床を直接的に変えていくことの意義と面白さを実感し、それが現在の研究活動の原点となっています。
これまで、EGUIDEプロジェクトの多施設データを用いた研究や、うつ病・統合失調症の治療ガイドライン遵守行動に関する解析に携わり、自施設データの詳細な調査や大規模データ解析を進めてきました。特に、EGUIDE講習受講とガイドライン遵守の関係、重症度記載の媒介効果、治療選択への影響といったテーマについて検証を行い、複数の学会発表や査読付き論文として成果を発信してきました。現在も複数の原稿を並行して執筆・投稿準備中です。
このような研究活動を、医局長・病棟長・リエゾン長といった多忙な役職を担いながら継続できている大きな理由の一つが、橋本先生による週1回30分〜1時間のオンライン指導です。短時間ながらも極めて実践的かつ的確なご指導をいただけるため、限られた時間の中でも着実に研究を前進させることができています。解析に至るまでの過程で、膨大なデータの整理・品質管理や先行研究の徹底的な読み込みといった基礎的な作業の重要性を学び、これが現在の研究力の土台になっていると実感しています。
現在では、EGUIDEの定例ミーティングや解析チームのディスカッションにも継続的に参加し、次のステップとなる研究計画の立案・実装にも関わるようになりましたが、こうした一連のステップアップもすべて橋本先生の丁寧なご指導と継続的なご助言のおかげだと感じています。限られた時間でも、積み重ねた基礎とオンライン指導を最大限に活かすことで、数年前と比べて確実に研究者としての視野と実力が広がりました。本稿が、当講座やEGUIDEプロジェクトへの参加を検討されている先生方のご参考になれば幸いです。
2025年10月13日
講師、客員研究員(月1~2回:研究者育成道場オンラインフェロー)
精神科医14年目から始めた先生の声
私は現在、精神科医として14年目を迎え、地方大学で外来診療、学生教育、医局員の研究指導に携わっています。所属大学がEGUIDEプロジェクトに参加したことをきっかけにEGUIDEの活動に関わるようになり、そのご縁から、このようなオンライン国内留学の機会をいただきました。
現在はオンラインで月1〜2回、研究に関するアドバイスを受けています。研究テーマの設定方法から進め方に至るまで幅広くご指導いただけるほか、科研費をはじめとする研究費申請書類についても丁寧に添削していただいています。研究テーマは必ずしも特定の研究室のテーマに限らず、自施設で取り組んでいる研究内容についてもご相談できる点が大きな魅力です。申請書の作成については、これまで書籍などを参考に独学で学んできましたが、実際に数多くの研究費を獲得されてきた先生から伺うコツや注意点には、学ぶべき点が非常に多いと感じています。ここで得た知識や経験は、自らのスキルアップに繋がるだけでなく、後輩の研究指導にも還元できています。
特に地方にいると、情報交換のために移動するにも時間や調整が必要ですが、オンラインであればそうした負担なく面会できるのが大きな強みです。このオンライン国内留学は、大学院生や大学院を修了した先生方に限らず、研究指導に携わっている先生方にとっても有益な機会だと思います。興味をお持ちの先生がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に取り組んでみましょう。
2025年10月2日
准教授、客員研究員(月1~2回:研究者育成道場オンラインフェロー)
精神科医14年目から始めた先生の声
橋本亮太先生からのご指導を振り返って
私が橋本亮太先生からご指導をいただくようになったのは、EGUIDEにおいて「研究者育成道場」が立ち上がり、入門者を募集していた時期でした。研究者としての力を体系的に学びたいと考え、入門を決意したことが大きなきっかけとなりました。以後、1~2週に1回、30分から1時間のご指導を継続していただき、その中で研究の進め方や論文作成における基本姿勢を徹底的に学んできました。
ご指導の特徴は、単に結果を出すことにとどまらず、「科学的に重要な点をどう主張するか」「論文全体の質をいかに高めるか」という視点を常に意識させてくださる点にあります。課題として取り組んでいるのは、EGUIDEの膨大なデータを用いた「ガイドライン講習が受講者本人のみならず、その同僚や組織文化にも影響を与える」というテーマであり、先生はこの研究の意義と社会的な広がりを常に示してくださいました。
指導を受けて特に印象的だったのは、自分では「これで十分だろう」と考えた箇所が、科学的にどのように足りていないのかを正確に指摘していただけることです。想定される読者にとって何が理解しやすく、何が分かりにくいのかを意識し、それに応える形で論文を構築することの大切さを実感しました。こうした経験を経て、自分自身の論理的に考える力が格段に向上したと感じています。
先生のお言葉の中で強く心に残っているのは、「理解されないと評価されないんだよ。理解されるために全力でやるんだよ。」という言葉です。これは研究を進める上での姿勢そのものを示しており、常に自分を奮い立たせてくれる指針となっています。ご指導は時に厳しいものですが、ふとした瞬間にいただくお褒めの言葉は大きな励みとなり、研究を続ける活力につながっています。
この約1年間を振り返ると、先生からいただいたご指導は、自分にとって大きな転換点であり、研究者としての基盤を築く貴重な経験となりました。今後もこの学びを糧に、さらなる研究に邁進するとともに、EGUIDEの価値を研究・教育・臨床の場で広めていきたいと考えています。
2025年10月4日
助教(1~2週に1回:研究者育成道場オンラインフェロー)
精神科医16年目から始めた先生の声
大学医学部附属病院精神科のと申します。現在、精神科医として17年目、大学病院に所属して10年を超えました。私は当初、一般の総合病院精神科に後期研修医として就職し、精神保健指定医および精神科専門医を取得した後に大学の医局に入局しました。その後、臨床や教育の傍ら研究活動を開始し、紆余曲折を経て学位を取得しました。学位を取得する頃には、私生活においてもある程度の基盤ができており、留学などを考えても実現は難しい状況にありました。
そのような時期に、以前からEGUIDEなどで大変お世話になっている橋本先生から、研究者育成のための個人面談および研究者同士の意見交換の場への参加を勧めていただきました。研究者としての力不足を痛感していたこともあり、参加を希望しました。
現在は、月に1〜2回のWeb個人面談と、月1回の情報交換会に参加しています。研究計画の立案から、得られた結果の解釈、申請書の作成まで、一つひとつ丁寧にご指導いただき、そのたびに新たな発見と成長を感じています。
臨床業務や学生教育に追われ、なかなか研究に割ける時間は限られていますが、学んだことを活かし、短い時間でも着実に前進できるよう努めていきたいと考えています。
2025年9月29日
講師、客員研究員(月1~2回Web個人面談+月1回情報交換会:研究者育成道場オンラインフェロー)
精神科医17年目から始めた先生の声
大学健康管理センター・精神医学講座のと申します。現在、医師20年目、精神科18年目です。大学では医局業務と臨床を行いながら研究に取り組んでいます。現在は、週に約1時間の橋本先生との個別会議に加え、月に1回の研究者育成道場会議、さらに3つのグループに分かれて月1回ずつ行われる会議に参加し、研究活動を進めています。研究者育成道場は、日常診療を続けながら研究スキルを段階的に身につけられる環境であり、限られた時間でも確実に力を伸ばすことができる場だと感じています。
これまで私は基礎研究にも携わり、マウントサイナイ大学での留学経験もありました。また、臨床研究として近赤外線スペクトロスコピー(NIRS)や事象関連電位(ERP)を用いた検討も行ってきました。しかし、EGUIDEのように万単位の症例を対象としたビッグデータ解析に携わる機会はこれまでなく、その新しい挑戦と可能性に強く惹かれました。ちょうどその頃、飲み会の席で橋本先生から道場参加のお誘いをいただいたことが大きな契機となり、研究者育成道場に加わることを決めました。
参加後は、EGUIDEデータを用いて「実践度」という診療行動に関わるスコアと実際の診療行動との関連を調べました。その過程で過去のEGUIDE関連論文を集中的に読み込み、半年程度で論文投稿に至ることができました。さらに現在は、次の論文作成や学会発表を進めており、複数のテーマを並行して展開しています。研究者育成道場での活動を通じ、臨床データを客観的に解析する視点を養い、診療行動や教育効果をエビデンスに基づいて検証する力を高められたと実感しています。
加えて、この道場を通じて他大学の先生方とつながりを持てたことは、私にとって何よりの財産です。普段はそれぞれの医局で臨床や教育に従事している先生方が、道場という共通の場に集まり、研究の進め方やデータの解釈、論文化の工夫について率直に意見交換できることは大変刺激的です。自分の研究テーマを他大学の視点から批判的かつ建設的に検討していただけることで、新しい気づきが得られると同時に、自分の研究の位置づけや方向性を客観的に見直す機会となっています。
さらに、他大学の先生方と協働する中で、同じテーマに関心を持つ仲間として自然に交流が深まり、共同研究の芽が生まれることもあります。こうした横のつながりは、自身の研究の幅を広げるだけでなく、将来的に学会や研究会の場で支え合い、高め合う人的ネットワークへと発展していく可能性を秘めています。精神科臨床や研究を長く続けていく上で、このような人との出会いやつながりが大きな力になると強く感じています。
2025年9月29日
センター長、客員研究員(週1回:研究者育成道場オンラインフェロー)
精神科医18年目から始めた先生の声
私は医師として21年目になります。私は、大学病院で勤務しておりますので、臨床と教育と研究を日々の業務として行っております。
EGUIDE講習はEGUIDE講習開始初期の頃に受講いたしまして、その際診療ガイドラインを普及しエビデンスと日常臨床のギャップを埋め、より質の高い治療を広く届けたいというEGUIDEの理念に共感し、現在では指導医として講習に協力させていただくとともに、研究活動にも取り組んでおり、臨床・教育・研究のすべてに直結する学びを得ています。
これまで、EGUIDEプロジェクトの講習効果を確認するための多施設データを活用し、特に治療抵抗性統合失調症とクロザピンに関する研究を行い、「退院時のクロザピン処方の有無における抗精神病薬単剤療法率および向精神薬併用率」や「クロザピン処方体制や治療抵抗性統合失調症に関する診断の有無と抗精神病薬単剤療法率との関連」を解析し、複数の学会発表や査読付き論文として成果を報告いたしました。さらに、発展的な研究として「統合失調症治療におけるベンゾジアゼピン受容体作動薬の処方と便秘薬使用リスクの関連性」を解析し、こちらも学会発表や査読付き論文として報告いたしました。
こうした研究を行うことができましたのも、EGUIDEでの月1回の定例ミーティングおよび橋本先生による1~2週に1度30分〜1時間のオンライン指導の存在が大きいです。ミーティング中でも様々なご助言を橋本先生にいただきつつ、さらにオンライン指導では、自身の研究推進だけでなく、他の先生方を指導する際の方法論についても、丁寧にご教授いただいております。まさに橋本先生の「秘伝」を授けていただいているような貴重な機会だと感じております。
このように限られた時間でも、オンライン指導を受けることで、自身の論文発表などの成果だけでなく、後進を導く指導者としての視点や実力も身に着けることができています。本稿が、当講座やEGUIDEプロジェクトへの参加を検討されている先生方にとって、少しでも参考となれば幸いです。
2025年10月20日
講師、客員研究員(研究者育成道場オンラインフェロー)
常勤研究者
研究者としてキャリアを積みたい精神科医には、当部に常勤研究者として在籍し、COCOROやEGUIDEなどの当研究部で推進している研究に携わっていく道もあります。個別にご相談に応じますのでお問い合わせください。
精神科医11年目から始めた先生の声
私は2009年に母校の神経精神医学講座に入局し、同時に大学院にも入学して、精神科専門医研修と並行して精神疾患の死後脳研究で学位を取得しました。研究を続けながら臨床経験も積み、精神科専門医、精神保健指定医を取得してからカロリンスカ研究所への海外留学も経て、帰国後も大学で臨床、教育、研究を担当していました。その後、縁あって2019年に国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 精神疾患病態研究部に赴任しました(基盤整備研究室長)。
研究分野は死後脳研究から脳画像研究に移り、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 精神疾患病態研究部に来てからはCOCORO(Cognitive Genetics Collaborative Research Organization−認知ゲノム共同研究機構)における多施設大規模研究を担当しております。
現代の精神科でも、診断は主観的な行動・心理症状で判断されていますが、生物学的な病態に基づいた治療法開発のために客観的な指標に基づく新たな診断概念が求められています。その第一歩として私たちは側脳室拡大(Enlarged Ventricle: EV)と認知機能障害(Cognitive Impairment: CI)をバイオマーカーとしたEVCI(EV + CI)という新たな精神疾患をデータ駆動型に発見、報告し、EVCIのさらなる病態解明のためにCOCOROの多施設でデータを前向きに収集し、その縦断的病態解明を進めています。
私たちと一緒に精神疾患の病態解明を目指し、精神科の世界を変えてくれる仲間を募集しています!
2025年10月10日
室長(常勤)
| 仕事内容 |
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神疾患病態研究部では、日本を代表する精神医学多施設共同研究体である
COCOROを牽引し、統合失調症、気分障害、発達障害等の臨床研究データ、バイオリソース等の収集、蓄積及び管理を行い、新たな疾患分類による病態解明と診断法・治療法の開発を行っています。 ※上記について関心が高く、研究チームのメンバーとして意欲的に研究を推進することができることが求められます。研究の進捗によってはこれら以外の作業を行うことがあります。また、一般的なPC操作スキル(ワード、エクセル、メール、インターネット)、他職種との調整等を行うため、コミュニケーション能力や協調性などが必要となります。 |
|---|---|
| 応募資格 |
|
| 待遇等 |
ご経験、勤務年数、能力によって変わります。 科研費研究員をご参照ください。大学院生の受け入れなどもしておりますので、個別にお問い合わせください。 |

橋本亮太 ryotahashimoto55@ncnp.go.jp
- 学生アルバイト・研究生・研究員
- 精神科医
- 心理士
- 研究補助スタッフ
- 事務スタッフ