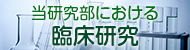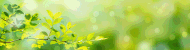統合失調症診断医療機器プログラム研究
(Schizophrenia Diagnostic Medical Device Program:略称SDM研究)
精神疾患の診断は医師の問診に基づく主観的評価が主体となるため、症状が不明確な発症早期での診断の一致率は低くなることが知られています。代表的な精神疾患である統合失調症は早期治療によりその予後が改善することが知られていますが、発症早期は症状がはっきりせず、その経過も短く診断が困難です。従って、発症早期に現れる客観的かつ科学的なマーカーを明らかにし、診療現場で測定することが望まれています。統合失調症では、認知社会機能、視線、脳神経画像などの異常が繰り返し報告されていることから、これらの検査データやデジタルフェノタイピングデータを用いた総合判断を行うことによって診断を行うことが可能となると考えられます。本研究においては、血液、画像、認知機能などの検査データと、視線や発語などデジタルフェノタイピングデータを用いて、統合失調症の診断を可能にする医療機器プログラムの開発を行います。尚、本研究は、日本医療研究開発機構 医工連携・人工知能実装研究事業(研究課題名:AI技術を活用した統合失調症の早期診断医療機器プログラムの開発に関する研究、研究開発代表者:橋本亮太)の支援のもとに実施されております。また、特定臨床研究として登録されております。
お申込みご希望の方は、下記Emailまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。メールでお申し込みの場合は、件名に「研究ボランティア応募」と書いて空メールをお送りください。
【お問い合わせ先(研究ボランティア係)】
国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 精神疾患病態研究部
〒187-8553 東京都小平市小川東町4-1-1
Tel:042-346-1798
E-mail: byoutaijim06@ncnp.go.jp
タブレットを用いた医療機器プログラム

本研究では、認知・社会機能や視線などのフェノタイプをタブレットを用いて簡便に測定・自動解析できるようにします。従来は、認知・社会機能検査は紙と鉛筆を用いて心理士が患者と対面で行っていました。また、視線検査はハイスペックの研究用機器で研究者が測定していました。本研究では、これを簡便にタブレットで測定できる新しい技術を開発しますが、この新技術は、精神科領域においては人が対面で診察や検査を行うという現状からのパラダイムシフトとなるでしょう。
AI技術による医療のサポート
深層学習・機械学習モデル等のAI技術を活用して、解析の精度の向上を目指します。より有効な特徴を抽出して、統合失調症の鑑別の精度向上や、リスクが低い場合に除外する際の新たな方法論を探求します。医療者とAIのコラボレーションによる、新しい診断の在り方を示します。