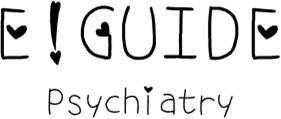統合失調症およびうつ病における、施設のガイドライン推奨治療実施率に対するEGUIDE講習の長期的な影響:多施設共同研究
概要
診療ガイドラインは、エビデンスに基づいて作成され、患者と医療者の意思決定の際に用いられます。しかし、臨床現場において必ずしも適切に用いられておらず、ガイドラインの推奨治療と実臨床の治療内容との隔たりも指摘されています。この問題を解決すべく、「精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に関する研究(EGUIDEプロジェクト)」が2016年に開始され、現在まで継続されています。
ガイドライン講習への参加によりガイドライン推奨治療実施率が向上することは過去の短期的な調査より報告されていますが、長期的な効果や参加医師の所属施設への影響は不明でした。そこで本研究ではロジスティクス回帰分析を用い、施設の講習参加後経過年数によるガイドライン推奨治療実施率の変化を評価し、参加医師がもたらす施設への波及効果の有無を検討しました(表1,2)。
結果、統合失調症では7項目(治療抵抗性統合失調症の検討、他の向精神薬の併用もない抗精神病薬単剤治療、抗不安薬・睡眠薬の非処方、抗コリン薬の非処方、持効性注射剤治療、クロザピン治療、mECT治療、向精神薬の頓服薬の非処方)、うつ病では2項目(重症度の診断、mECT治療)のガイドライン推奨治療実施率が年々増加していくことが明らかになりました。ガイドライン講習に参加することで、参加医師だけでなく所属施設全体の治療の質が時間経過と共に向上していくことが示唆されました。

<今回の結果を踏まえ、精神科医師の皆様に以下を提案します>
- EGUIDEプロジェクトが実施するガイドライン講習に参加しましょう。施設内に参加医師がいることでその効果が波及し、施設全体の医療の質が向上する可能性があります。
- 日々の変化はわずかでも、それを継続的に実施すれば施設全体の医療の質は良くなっていきます。ガイドライン推奨治療を意識し、目の前の患者さんがより良い治療を受けられるような努力を継続的に行いましょう。
この内容は「Neuropsychopharmacology Reports」に掲載されました。 原文はこちら